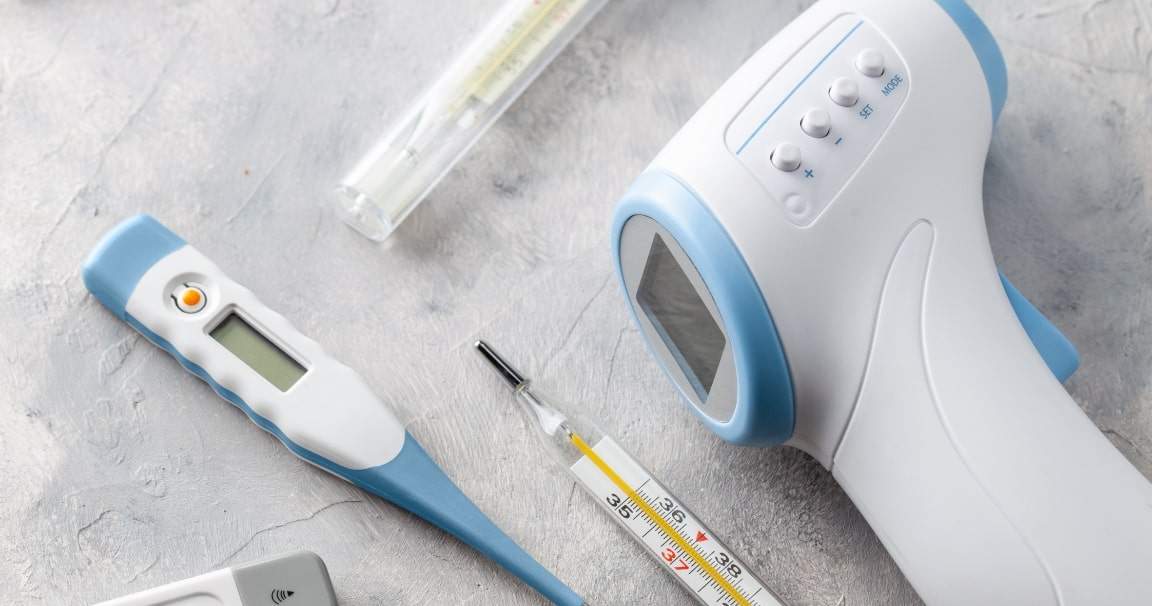夢の内容を実際に体で演じる
こんな症状はありませんか?
- 「寝ている間に叫んだり、手足を激しく動かしたりしていると家族に指摘された」
- 「夢で戦っていた内容を実際に行動していたようで、パートナーを叩いてしまった」
- 「夢と現実の区別がつかず、飛び起きたり、ベッドから転落したりすることがある」
- 「夢で逃げたり戦ったりする内容が多く、翌朝はその内容を鮮明に覚えている」
- 「寝ている間に大声を出したり、奇声を発したりすることがある」
- 「寝相が非常に激しく、寝具が乱れていたり、物が落ちていたりする」
これらの症状は、「レム睡眠行動障害(REM Sleep Behavior Disorder: RBD)」と呼ばれる睡眠障害の可能性があります。通常、夢を見ている間(レム睡眠中)は体の筋肉が弛緩して動かなくなるのですが、この障害では筋肉の弛緩が失われ、夢の内容を実際に体で演じてしまいます。
レム睡眠行動障害とは
レム睡眠行動障害は、レム睡眠中(主に夢を見ている時期)に起こる異常行動です。通常、レム睡眠中は筋肉が一時的に麻痺状態(筋緊張抑制)になり、夢で体を動かしていても実際の身体は動きませんが、この障害ではその機能が失われることで以下のような症状が現れます:
- 夢の行動化:夢の中での動作(走る、戦う、避ける)を実際に体で行動してしまう
- 発声:会話、叫び声、うなり声などを発する
- 暴力的な動作:特に「追いかけられる」「攻撃される」といった夢に伴う防衛的な動き
- 負傷のリスク:ベッドからの転落、家具にぶつかるなどによる本人や同床者の負傷
- 夢の内容の記憶:行動後に目覚めると、関連した夢の内容を鮮明に覚えていることが多い
この障害は通常、睡眠の後半(明け方に近い時間帯)に多く発生し、高齢の男性に多いとされていますが、女性や若年層でも起こり得ます。
レム睡眠行動障害の主な原因
1. 特発性(原因不明)
- 明確な原因が特定できないケース
- 徐々に発症し、慢性的に続くことが多い
2. 神経変性疾患との関連
- パーキンソン病
- レビー小体型認知症
- 多系統萎縮症
重要なポイントとして、レム睡眠行動障害が上記のような神経変性疾患の前兆として現れることがあり、これらの疾患の発症前に数年〜数十年先行して出現することがあります。
3. 二次性(薬剤や疾患が原因)
- 抗うつ薬(特にSSRIやSNRIなど)の副作用
- 認知症などの神経疾患
- ナルコレプシー(過眠症)に伴うもの
- アルコールの離脱症状や薬物乱用
レム睡眠行動障害がもたらすリスク
- 本人の外傷:ベッドからの転落、壁や家具への衝突による怪我
- 同床者への危害:無意識の暴力的行動によるパートナーへの危険
- 睡眠の質の低下:頻繁な覚醒による睡眠不足
- 心理的ストレス:本人や家族の不安や心配
- 神経変性疾患の前兆:将来的な神経疾患発症のリスク
すみだ両国まちなかクリニックでの診療
当院の睡眠外来では、レム睡眠行動障害に対して以下のような診療・治療を行っています。
1. 詳しい問診と評価
- 症状の詳細(頻度、種類、強さなど)
- 同床者や家族からの情報収集(目撃情報が重要)
- 既往歴や服用中の薬の確認
- 神経学的症状の有無の確認
2. 診断のための評価
- 簡易検査による睡眠状態の評価
- 神経学的診察
- 必要に応じて専門医療機関での精密検査をご紹介
3. 治療とマネジメント
薬物療法
- 症状の程度に応じた適切な薬剤の処方
- 効果と副作用のバランスを考慮した投薬調整
安全対策の指導
- 寝室環境の安全確保の提案
- 転倒・外傷予防のアドバイス
基礎疾患への対応
- 原因となっている可能性のある薬剤の調整
- 神経変性疾患の早期発見と対応
- 必要に応じて神経内科など専門医療機関をご紹介
レム睡眠行動障害の症状がある方への安全対策
寝室環境の整備
- ベッド周囲の安全確保:ベッドサイドテーブルや鋭利な物を撤去
- 床にクッション材を敷く:転落時の衝撃を和らげる
- ベッドを低くする:転落の危険性を減らす
- ベッドガードの設置:転落防止策として検討
- 窓やガラス製品から距離を置く:衝突による危険を避ける
生活習慣の見直し
- 規則正しい睡眠スケジュール:毎日同じ時間に就寝・起床
- アルコールの制限:特に就寝前の飲酒を控える
- ストレス管理:リラクゼーション法や適度な運動の習慣化
- 睡眠薬や向精神薬の見直し:医師と相談の上、服用中の薬剤を再検討
同床者の保護
- 別々のベッドでの就寝:症状が強い場合は検討
- パートナーへの情報提供:症状の性質を理解してもらう
- 異常行動の兆候を認識する:早期に起こして症状を止める
こんな方は早めの受診をおすすめします
- 暴力的な夢内容の行動化がある
- 行動により自分自身やパートナーが怪我をした、またはそのリスクがある
- 症状が頻繁に(週に1回以上)起こる
- 60歳以上で症状が始まった
- 手の震えや動作の緩慢など、神経学的な症状も感じる
- 認知機能の低下が気になる
レム睡眠行動障害に関するよくある質問
Q: レム睡眠行動障害と普通の寝言や寝相の悪さとの違いは何ですか?
A: 普通の寝言や寝相の悪さは主にノンレム睡眠(浅い睡眠)で起こることが多く、行動も比較的穏やかです。それに対してレム睡眠行動障害では、鮮明な夢に伴う複雑で時に激しい行動が特徴で、目覚めた後に夢の内容を詳細に覚えていることが多いという違いがあります。
Q: パーキンソン病など神経疾患の前兆とのことですが、必ずそうなりますか?
A: レム睡眠行動障害がある方がすべて将来的に神経変性疾患を発症するわけではありません。ただし、長期研究によれば発症リスクは高まるため、定期的な診察や早期の兆候に注意することが重要です。
Q: 子供の夜驚症(夜泣き・夜驚)との違いは何ですか?
A: 夜驚症は主に深いノンレム睡眠中に起こり、子供に多く見られます。目覚めた後に出来事を覚えていないことが多く、成長とともに改善することが一般的です。一方、レム睡眠行動障害はレム睡眠中に起こり、成人(特に中高年)に多く、夢の内容を覚えていることが特徴です。
まとめ
レム睡眠行動障害は、夢の内容を実際に体で演じてしまう睡眠障害です。本人や周囲の人の安全を脅かす可能性があるだけでなく、将来的な神経疾患の前兆となる可能性もあるため、早期の適切な診断と対応が重要です。
この障害は「わざと」行動しているわけではなく、自動的に起こる神経学的な現象です。適切な治療と安全対策により、症状をコントロールし、リスクを軽減することが可能です。
すみだ両国まちなかクリニックでは、レム睡眠行動障害の症状がある方に対して、総合的な評価と個別化された治療プランをご提案します。「夢の内容を実際に行動してしまう」「寝ている間に暴れる」とご心配の方は、ぜひお気軽にご相談ください。