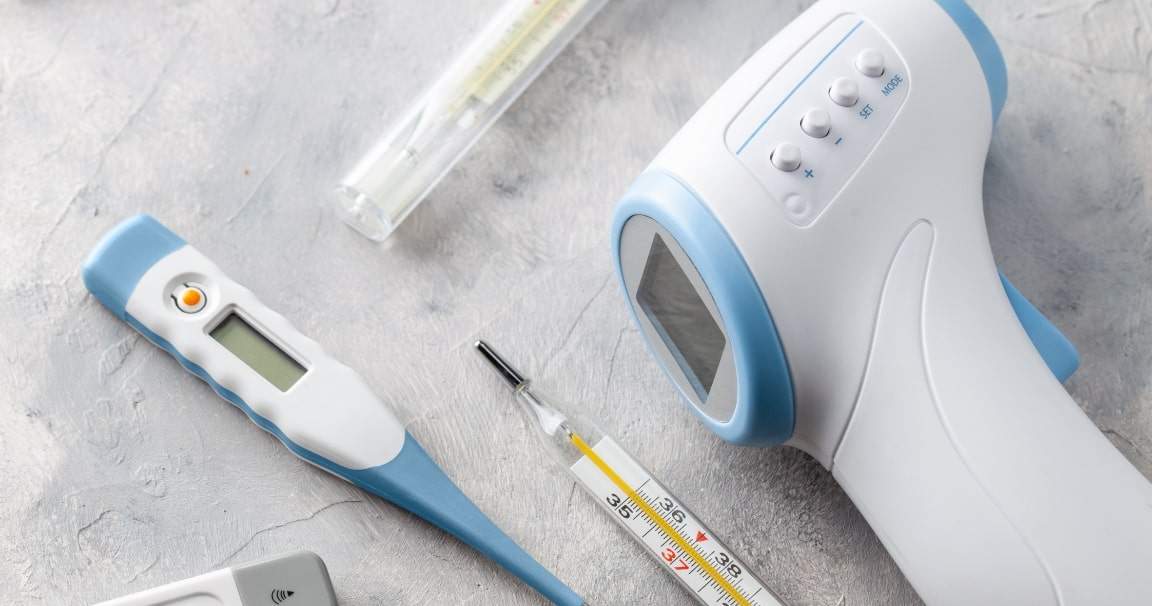小児科症状
3日以上便が出ていない
「子どもが3日以上お通じがない」「排便時に痛がって泣く」「便が硬くてコロコロしている」
お子さまの便秘は保護者の方にとって心配の種となりますが、小児の便秘は比較的よく見られる症状です。ただし、放置すると慢性化する恐れもあり、適切な対応が必要です。このページでは、小児の便秘の原因や対処法、受診の目安についてご説明します。
1.小児の便秘について
小児の便秘は、便が出にくい、排便回数が少ない、便が硬いなどの症状を指します。医学的には以下のような状態を便秘と考えることが多いです:
- 1週間の排便回数が3回未満
- 硬くて大きな便が出る
- 排便時に痛みを伴う
- 排便に強いいきみが必要
- 便を我慢する様子がある
年齢によって「正常」な排便回数は異なります:
- 乳児(母乳):1日数回~1週間に2~3回
- 乳児(ミルク):1日1~2回程度
- 幼児~学童:1日1回~2日に1回程度
2.小児の便秘の主な原因
- 機能性便秘(約95%)
- 排便習慣の乱れ(トイレトレーニング時の我慢など)
- 食生活の問題(食物繊維不足、水分摂取不足)
- 運動不足
- 心理的ストレス(環境の変化、入園・入学など)
- 便の我慢による「便秘の悪循環」(痛みを恐れて我慢→さらに硬くなる→より痛みが強くなる)
- 器質性便秘(約5%)
- 先天性の腸の異常(ヒルシュスプルング病など)
- 肛門の形態異常
- 脊髄の異常
- 甲状腺機能低下症などの内分泌疾患
- 腸の運動を抑制する薬剤の使用
3.便秘の兆候と注意すべきサイン
一般的な便秘の兆候:
- 排便間隔の延長(3日以上)
- 便が硬く大きい
- 排便時の痛みや不快感
- お腹の膨満感
- 食欲不振
- イライラや機嫌の悪さ
以下のような症状がある場合は、より注意が必要です:
- 血便がある
- 嘔吐を繰り返す
- 体重増加不良
- 発熱を伴う
- 腹痛が強く持続する
- 肛門周囲の異常な発赤・腫れ
- 生後間もない乳児(特に生後1ヶ月以内)の便秘
4.ご家庭でできる対応
- 食事の工夫
- 食物繊維を多く含む食品を取り入れる(野菜、果物、全粒穀物など)
- 年齢に応じた適切な水分摂取を心がける
- 乳児の場合:母乳・ミルクの適切な量と間隔
- 生活習慣の改善
- 規則的な排便習慣をつける(毎朝食後など)
- 適度な運動を促す
- ゆったりとした排便時間の確保
- トイレトレーニング中の工夫
- 焦らず、子どものペースを尊重
- 排便を我慢させない
- 便座に座る時間は5〜10分程度に
- 足台を使い、正しい姿勢(膝が腰より高い位置)で排便できるよう工夫
- 赤ちゃんの場合
- 優しく腹部をマッサージ(時計回りに)
- 足を曲げ伸ばしする体操
- 綿棒の先に潤滑油(ワセリンなど)をつけて肛門を優しく刺激(医師に相談の上)
5.受診すべきタイミング
以下のようなケースでは、医療機関への受診をお勧めします:
- 1週間以上便が出ていない
- 排便時の痛みが強く、子どもが怖がって排便を我慢する
- 腹痛や嘔吐を伴う
- 血便や粘液便がある
- 家庭での対応で改善しない
- 生後1ヶ月以内の新生児に便秘がある
- 便秘と下痢を繰り返す
- 成長や発達に影響が出ている
長期間放置すると便秘が慢性化し、治療が難しくなることがあります。心配な場合は早めに相談しましょう。
6.すみだ両国まちなかクリニックでのサポート
当院では、便秘でお困りのお子さまに対して以下の診療を行っています:
- 問診・診察
- 排便状況の詳細な確認(頻度、便の性状、痛みの有無など)
- 食生活や生活習慣の確認
- 腹部の触診
- 必要に応じて直腸診(高度な便秘の場合)
- 検査
- 必要に応じて血液検査(甲状腺機能など)
- 腹部の診察
- 治療
- 年齢や症状に応じた便軟化剤の処方
- グリセリン浣腸や坐薬の指導(必要な場合)
- 食事・生活指導
- 排便習慣の確立へのアドバイス
- フォローアップ
- 治療効果の確認
- 再発予防のための生活指導
器質的な問題が疑われる場合や、治療に反応しない重度の便秘の場合には、エコーなどの検査が必要と判断された際は、連携医療機関(小児消化器専門医など)をご紹介いたします。
7.慢性便秘への対応
便秘が3ヶ月以上続く慢性便秘の場合は、以下のような段階的な治療が必要になることがあります:
- 腸管内の便の除去(必要な場合)
- 浣腸や内服薬で溜まった便を出す
- 維持療法
- 便が柔らかく出やすい状態を維持するための薬物療法
- 一定期間(数ヶ月~1年程度)の継続が必要なことも
- 段階的な薬の減量
- 症状の改善に合わせて少しずつ薬を減らす
- 生活習慣の定着
- 規則的な食事と排便習慣
- 適切な水分・食物繊維の摂取
8.便秘予防のポイント
- バランスの良い食事
- 野菜、果物、穀物をバランスよく
- 乳製品の適度な摂取(ヨーグルトなど)
- 十分な水分摂取
- 年齢に応じた適切な量の水分を
- 規則正しい生活リズム
- 朝食後のトイレ習慣
- 十分な睡眠
- 適度な運動
- 腸の働きを活発にする
- 外遊びの奨励
- 排便サインを見逃さない
- 子どもが便意を訴えたらすぐにトイレに行かせる
- 排便を我慢させない環境づくり
9.まとめ
- 小児の便秘は比較的よく見られる症状ですが、放置すると慢性化することも
- 多くは機能性便秘(食生活や排便習慣の問題)だが、まれに器質的な原因もある
- 家庭での食事・生活習慣の改善が基本
- 症状が強い場合や長く続く場合は医療機関への相談を
- すみだ両国まちなかクリニックでは、お子さまの年齢や症状に合わせた適切な診療を提供
お子さまの便秘でお悩みの際は、すみだ両国まちなかクリニックにご相談ください。適切な診断と治療、生活指導を通じて、お子さまの快適な排便習慣の確立をサポートいたします。