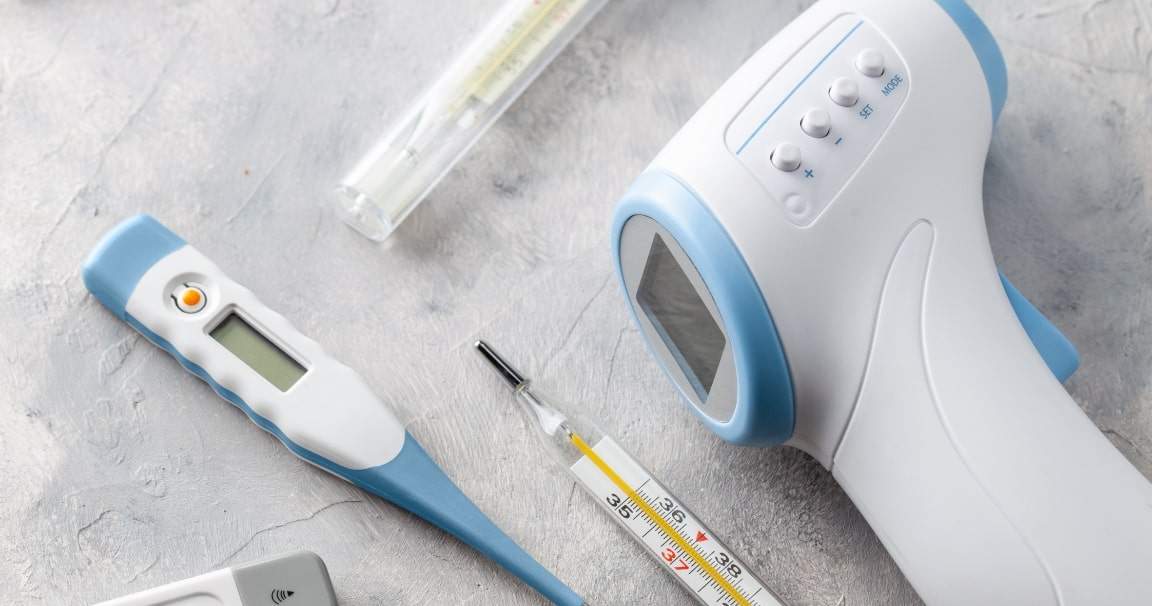小児科症状
呼吸時に肋骨の間がへこむ
「子どもが息をするたびに肋骨の間がへこんでいる」「呼吸が苦しそうで胸がペコペコする」
お子さまの呼吸時に肋骨の間(肋間)や鎖骨の下、胸の下部がへこむ症状は、医学的には「陥没呼吸(かんぼつこきゅう)」と呼ばれます。これは呼吸困難のサインであり、何らかの原因で気道が狭くなったり、肺に空気が十分に取り込めない状態を示しています。特に乳幼児は呼吸器系が未発達で気道が狭いため、軽度の炎症でも呼吸障害を起こしやすく注意が必要です。
1.陥没呼吸が起こる主な原因
- 喘息(ぜんそく)発作
- 気管支の炎症と収縮により、空気の通り道が狭くなる
- 特に呼気(息を吐くとき)が困難になり、ゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴を伴うことが多い
- クループ症候群
- ウイルス感染による声門下(喉の部分)の炎症・腫れ
- 特徴的な「犬の鳴き声」や「アザラシの鳴き声」のような咳
- 主に夜間に症状が悪化することが多い
- 細気管支炎
- RSウイルスなどによる細い気管支の炎症
- 特に生後2歳未満の乳幼児に多い
- 鼻水・咳に続いて呼吸困難が出現
- 肺炎
- 細菌やウイルスによる肺の炎症
- 高熱、咳、呼吸困難などの症状
- 乳幼児では重症化しやすい
- 気管支異物
- 食べ物や小さなおもちゃなどが気道に入り込んだ場合
- 突然の咳込みや呼吸困難
- 緊急対応が必要
2.陥没呼吸を伴う危険なサイン
以下のような症状が見られる場合は、緊急性が高く、すぐに医療機関を受診する必要があります:
- 呼吸が非常に速い(新生児・乳児:60回/分以上、幼児:40回/分以上)
- 唇や爪が青白い・紫色(チアノーゼ)
- 呼吸のたびに鼻翼(鼻の横)が大きく開く
- 息を吸うときに「ストライダー」と呼ばれる高い音がする
- 呼吸困難で会話や食事ができない
- ぐったりして反応が悪い
- 発熱が39℃以上で続く
特に乳児では症状が急速に悪化することがあるため、上記のサインが見られたらためらわず救急車を呼ぶことも考慮してください。
3.ご家庭でできる対応
緊急性の低い軽度の症状の場合、以下の対応が役立つ場合があります:
- 姿勢の工夫
- 上体を少し起こした姿勢をとらせる
- 乳児の場合は、抱っこして少し前かがみの姿勢にする
- 加湿
- 部屋の湿度を適切に保つ(50〜60%程度)
- 特にクループの場合は、浴室に蒸気を充満させその中で数分過ごすことで一時的に症状が和らぐことも
- 水分補給
- 脱水を防ぐため、少量ずつ頻回に水分を与える
- 安静にする
- 体を動かすと呼吸が苦しくなるため、静かに過ごさせる
ただし、これらの対応はあくまで医療機関に向かう間の応急処置や、軽度の症状の場合の対応です。症状が改善しない場合や悪化する場合は、すぐに医療機関を受診してください。
4.受診すべきタイミング
- 初めて陥没呼吸が見られた場合
- 上記の危険なサインがひとつでもある場合(緊急受診)
- 喘息やクループと診断されている子どもで、いつもより症状が重い場合
- 症状が徐々に悪化している場合
- 乳児(特に6ヶ月未満)で呼吸の異常がある場合
子どもの呼吸状態の変化は急速に進行することがあります。「様子を見よう」と判断に迷う場合は、医療機関に相談することをお勧めします。
5.すみだ両国まちなかクリニックでのサポート
当院では、呼吸困難や陥没呼吸のあるお子さまに対して以下の診療を行っています:
- 初期評価
- 問診(症状の経過、既往歴、アレルギー歴など)
- バイタルサイン(呼吸数、心拍数、酸素飽和度、体温)の測定
- 呼吸状態の詳細な診察
- 対応・治療
- 喘息発作:吸入薬(β刺激薬など)の処方・投与
- クループ:ステロイド薬の処方、必要に応じた吸入療法
- 感染症:原因に応じた薬剤(抗生物質など)の処方
- 酸素投与が必要な場合や重症例は、高次医療機関への紹介・搬送
- フォローアップ
- 症状に応じた再診の調整
- 家庭でのケア方法の指導
- 予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌など)の案内
緊急性の高い呼吸困難の場合や、肺炎などの詳細な評価が必要な場合には、エコー、レントゲンなどの検査が必要と判断された際は、連携医療機関をご紹介いたします。
6.喘息やアレルギー性疾患を持つお子さまへの対応
喘息と診断されているお子さまでは、定期的な通院と以下の点に注意することが大切です:
- 発作時の対応プラン(アクションプラン)を医師と相談して作成
- 吸入薬の正しい使用方法の習得
- 定期的な予防薬の使用
- 症状日誌をつけて、悪化因子を特定
- アレルゲンの回避(ハウスダスト対策など)
7.予防のポイント
- 感染予防
- 手洗い・うがいの習慣
- 流行期にはマスク着用(年齢に応じて)
- 予防接種の適切な接種
- 環境調整
- 受動喫煙を避ける(タバコの煙は呼吸器疾患を悪化させる大きな要因)
- 部屋の清掃と適切な湿度管理
- アレルギーがある場合は、ダニ・ほこり対策
- 早期対応
- 風邪症状がある時点で適切な休息と水分摂取
- 喘息持ちのお子さまは早めの対応で発作を軽減
8.まとめ
- 呼吸時の肋骨間のへこみ(陥没呼吸)は、呼吸困難の重要なサインです
- 喘息、クループ、細気管支炎、肺炎など様々な原因で起こり得ます
- 唇の色が変わる、呼吸が非常に速いなどの危険サインがある場合は緊急受診を
- 特に乳幼児は呼吸状態が急速に悪化することがあるため、早めの対応が重要
- すみだ両国まちなかクリニックでは、症状の評価と適切な初期対応、必要に応じた専門医療機関への紹介を行っています
お子さまの呼吸が心配な場合は、ためらわずにすみだ両国まちなかクリニックにご相談ください。お子さまの健康と安全を最優先に対応いたします。