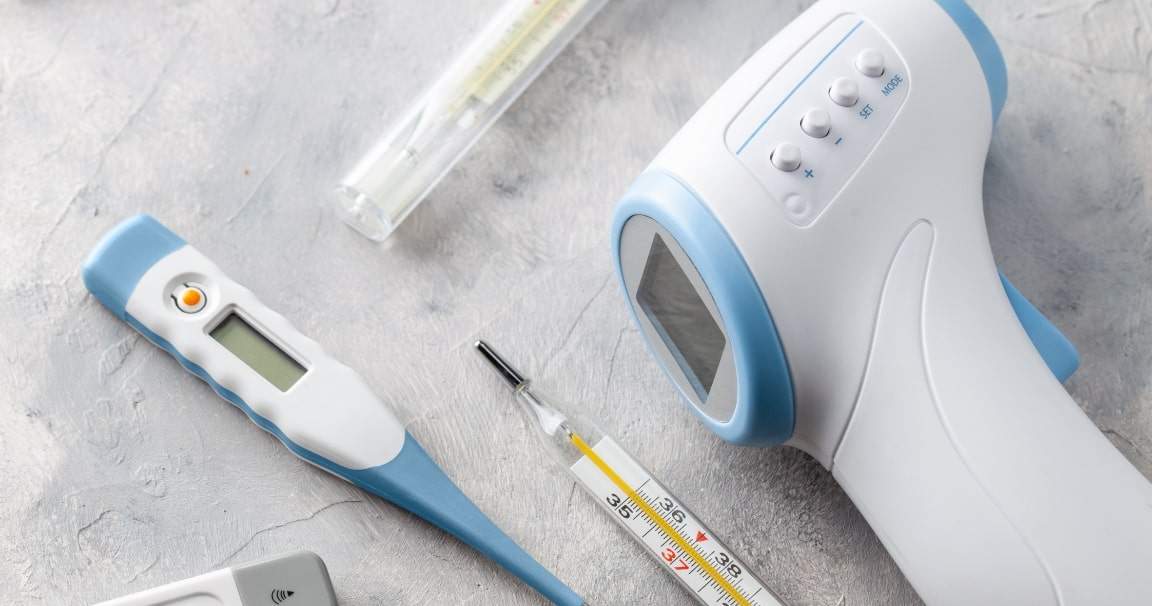内科症状
異常な多尿・のどの渇き… その症状、放っておくと危険かも?
「やたらと水を飲んでもすぐにまた喉が渇く」「トイレに行く回数が増えて、夜も眠りが浅い」
こんな“多尿”と“のどの渇き”が続いているとき、単なる水分摂りすぎでは済まないケースもあります。特に糖尿病をはじめとする生活習慣病や、ホルモン異常が関わっている可能性も。早期に原因を確かめないと、血管や臓器にダメージが蓄積してしまうかもしれません。ここでは、異常な多尿・のどの渇きを訴える際に疑われる原因や、早めに受診すべきポイントをまとめました。
なぜ「多尿・のどの渇き」が起こるの?
- 糖尿病(高血糖)
- 血糖値が高くなると、体が糖分を尿から排出しようとするため、尿量が増加してしまう
- 尿とともに水分も多く失われるため、そのぶんのどが渇いて水分を欲する「多飲多尿」が代表的な症状
- 腎機能の異常
- 腎臓のろ過機能が低下すると、体内で水分を保持しづらくなり、結果として尿量が増えることがある
- 腎臓のろ過機能が低下すると、体内で水分を保持しづらくなり、結果として尿量が増えることがある
- ホルモンのバランス異常
- 「尿崩症(にょうほうしょう)」など、抗利尿ホルモンの働きが乱れた場合に、多量の尿が出て強いのどの渇きを感じる
- 薬の副作用や過度な水分摂取
- 一部の薬(利尿剤など)は多尿を引き起こす場合がある
- 極端に水を飲みすぎる人は、一時的に多尿になるが、通常は頻繁に起こるものではない
こんな症状があれば要注意
- 夜中に何度もトイレに起きてしまう
- 水をたくさん飲んでも、またすぐ喉が渇く
- 甘いものを食べたあと、特にのどの渇きがひどい
- 体重が減ってきた、疲れやすい、だるさが続く
- 尿が泡立つ・においが強いなど、変化がある
こうした症状が長引く場合、自己判断で放置すると生活の質が下がるだけでなく、深刻な病状を見逃す恐れが高まります。
可能性のある病気を知っておこう
- 糖尿病
- 血糖値を下げるインスリンが十分に働かない・分泌されないことで、高血糖状態が持続
- のどの渇き、多尿、体重減少、疲労感などが代表的症状
- 慢性腎障害
- 尿のろ過がうまくいかず、余分な水分をうまく調整できなくなる
- むくみや血圧上昇も起こりやすい
- 尿崩症
- 抗利尿ホルモン(ADH)の分泌・作用異常で、非常に大量の薄い尿が出る
- 喉が常に渇き、水を欲する状態が続く
自分でできる対策と確認ポイント
- 適度な水分補給
- のどが渇くからといって甘いジュースやスポーツドリンクを過剰に飲むのは血糖値をさらに上げる可能性も
- 水やお茶を中心に、体調を見ながら補給
- 食生活の見直し
- 糖質や脂質を摂りすぎていないか確認
- 野菜やたんぱく質をバランスよく摂ることで血糖コントロールをサポート
- 定期的な運動
- 軽いウォーキングやストレッチでも糖の代謝を促し、体内のバランス維持に役立つ
- 健康診断を活用
- 血糖値やHbA1c、腎機能の指標(クレアチニン、eGFRなど)を把握
- 異常があれば早期対応が可能になる
受診の目安
- のどの渇きと多尿が2週間以上続いている
- 夜間の頻尿が多く、睡眠不足で日中がつらい
- 体重減少や疲れやすさを感じる
- 家族に糖尿病や腎疾患の人が多い(遺伝的リスクにも注意)
こうしたケースでは、自己流で水分や食事を制限するだけでは不十分。医師の診察で根本原因を突き止めるのが早期回復・予防につながります。
すみだ両国まちなかクリニックでのサポート
当院では、異常な多尿・のどの渇きを訴える患者さんに対し、以下のような診療を行っています。
- 血液検査(血糖値・HbA1c・腎機能)や尿検査で、糖尿病・腎疾患・ホルモン異常をチェック
- 必要に応じて超音波検査(腎臓の状態を確認)やホルモン検査など追加検査(専門医療機関へご紹介させていただく場合もございます。)
- 原因が糖尿病の場合は、生活習慣指導や薬物療法(血糖降下薬、インスリン注射など)
- 腎機能異常が見られれば、塩分制限や生活指導、必要に応じて専門医療機関への紹介
- 生活習慣改善(食事・運動)をサポートし、再発や合併症を防ぐ
「ただの水分摂りすぎかも」と思っていても、実は慢性疾患のサインである場合が少なくありません。気になる症状があるなら、一度受診して原因を特定し、適切な対策を始めましょう。すみだ両国まちなかクリニックがあなたの健康管理をしっかりサポートいたします。