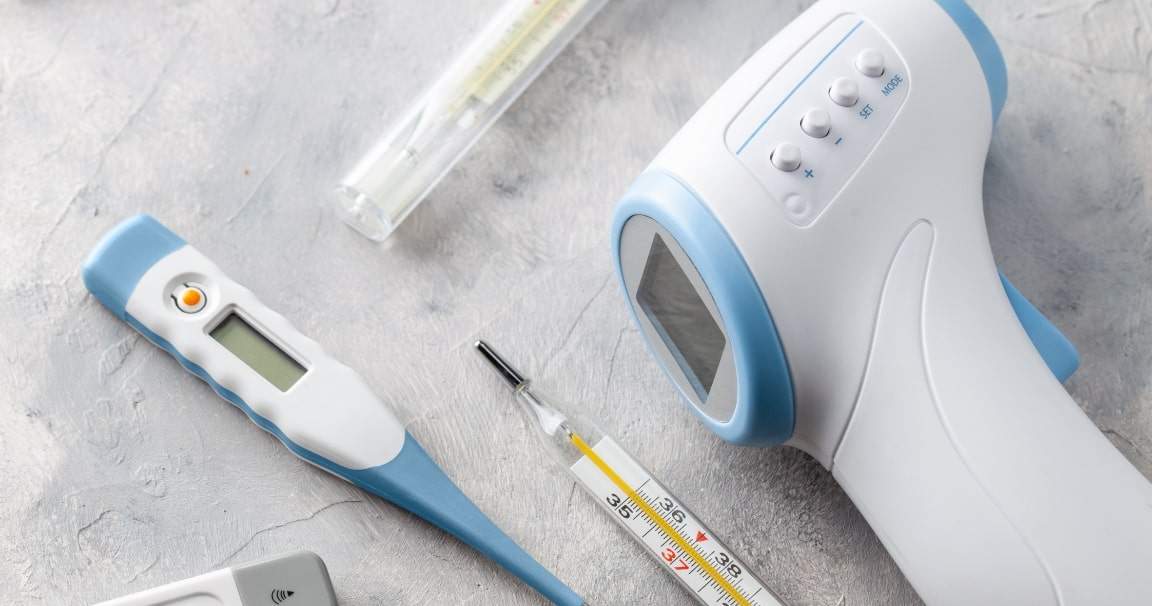- TSH(甲状腺刺激ホルモン)
脳の下垂体から出る「甲状腺を働かせる指令」。
- 甲状腺ホルモンが足りない → TSHが上がる(低下ぎみのサイン)
- 甲状腺ホルモンが多すぎる → TSHが下がる(働きすぎのサイン)
- 甲状腺ホルモンが足りない → TSHが上がる(低下ぎみのサイン)
- FT4(遊離サイロキシン)
甲状腺ホルモンの“実働部”。体の中で実際に効いている分を示します。
TSHだけでは判断が難しい時(脳側の病気が疑わしい時、重い病気で一時的に数値が乱れている時など)に特に役立ちます。 - 方法:通常の採血(血清)。
- 食事:原則いつでも可(空腹でなくてOK)。
- 比べ方:経過を見るときは、できるだけ同じ時間帯・同じ検査室で測るとブレが少なくなります。
- 追加の調べ方:まずTSHを測り、異常が出たらFT4(必要なら別のホルモンT3)を自動で追加して調べる運用にすると効率的です。
- ビオチン(美容・育毛系サプリに多い)は数値を誤判定させることがあります。2〜3日前から中止を。
- 薬:アミオダロン、リチウム、ステロイド、ドパミン製剤などは数値に影響します。
- 治療中のがん免疫薬(免疫チェックポイント阻害薬)は、甲状腺の炎症→機能低下を起こすことがあります。
- 海藻のとり過ぎ・造影剤検査の後は、一時的に数値が変わることがあります。
- 妊娠中・産後は基準範囲や見方が変わります。必ず申告を。
- だるい・眠い/寒がり/体重増加/便秘/肌の乾燥・抜け毛/むくみ/脈が遅い/気分が落ち込む/月経不順・不妊
- 検査でLDLコレステロール高め、CK(筋肉の酵素)軽く高めになることも
- 動悸・息切れ/手のふるえ/暑がり・汗が多い/体重減少・食欲増加/下痢ぎみ/イライラ・不眠/筋力低下
- 放っておくと心房細動や骨量低下のリスク
- 首の前のふくらみ・しこり/片側の違和感/声のかすれ/飲みこみにくさ
※無症状で超音波検査(エコー検査)ではじめて見つかることも多いです。 - 無痛性:しばらく働きすぎ→その後働き不足に移ることがあります
- 亜急性:発熱+前頸部の強い痛み、触ると痛い、血液で炎症反応が高い
- 第一歩はTSH。
- TSHが高い → まずFT4で重さを確認。必要に応じて甲状腺に対する抗体(橋本病の関与を見る検査)も。
- TSHが低い → FT4(+必要ならT3)で強さを確認。必要に応じてバセドウ病に関連する抗体も。
- TSHが正常でも症状が強い、首が腫れている、しこりがある → 甲状腺エコーを検討。
- TSHが高い → まずFT4で重さを確認。必要に応じて甲状腺に対する抗体(橋本病の関与を見る検査)も。
- 脳側の病気が疑われるとき(FT4が低いのにTSHが低い〜正常など)は、内分泌の精密検査が必要になります。
- 重い病気や手術の直後は、体の防御反応で一時的に甲状腺の数値が乱れることがあります。回復後に改めて測り直すと正確です。
- TSHが少し高い・FT4は正常(軽い“低下ぎみ”)
- TSHが10を超える場合は治療を考えるのが一般的。
- 10以下なら、症状の強さ、甲状腺に対する抗体の有無、心臓・血管のリスク、妊娠希望などを見て判断。まずは3〜6か月で再検し、続いているかを確認します。
- TSHが10を超える場合は治療を考えるのが一般的。
- TSHがしっかり低い・FT4/T3は正常(軽い“働きすぎ”)
- TSHが0.1未満で、高齢・骨粗しょう症・不整脈の危険がある方は治療を積極的に検討します。
- TSHが0.1未満で、高齢・骨粗しょう症・不整脈の危険がある方は治療を積極的に検討します。
- 妊娠中はTSHが生理的に下がります。可能ならその医療機関専用の基準範囲で判定します(ない場合は妊娠初期のTSH上限を約4.0の目安で判断)。
- 産後は一時的に働きすぎ→その後働き不足へと揺れることがあり、段階的な再検が役立ちます。
- ビオチン(サプリ):TSHが低く出る/T3・T4が高く出るなどの誤判定 → 2〜3日前から中止。
- アミオダロン・リチウム:働き不足/働きすぎのいずれも起こし得る → 定期的な採血が必要。
- がん免疫薬:甲状腺炎から働き不足へ → 4〜12週ごとの採血を。
- 海藻のとり過ぎ・造影剤検査後:一時的に数値が変わることがあります。
- 目安:危険度が高い特徴がそろう場合は1cm以上、中くらいなら1.5cm以上、低めなら2.5cm以上で検討。
- それ未満は、経過観察(1年ごとなど)で十分なことも多いです。
- 上記の症状が2つ以上あり、2〜4週間以上続く
- 首の腫れ・しこりに気づいた/家族に指摘された/声がかれる
- 健診でLDL高め、CK高め、貧血などの異常があるが原因が不明
- 産後1年以内で体調が戻らない、月経異常・不妊が気になる
- 高齢+体重減少や動悸が目立つ、不整脈・骨粗しょう症がある
- アミオダロン・リチウムを内服中、がん免疫薬で治療中
- 造影検査後や海藻のとり過ぎの後から体調が変化
- 家族に甲状腺の病気がいる/自己免疫の病気がある
- 強い動悸・息切れ、胸の痛み、意識がもうろう
- 発熱+首の強い痛み(亜急性甲状腺炎が疑われる)
- 極端に遅い/速い脈、ひどい脱水や衰弱
- 入口はTSH、必要に応じてFT4。
- 妊娠・産後、薬やサプリ、海藻・造影剤などの「数値がズレやすい条件」をあらかじめ伝えると、正確な判断につながります。
院長コラム
健康診断で見逃さない!甲状腺異常の早期発見
健康診断だけでは甲状腺の病気が見つかりにくいことがあります。
最初に調べるのはTSH(ティーエスエイチ:甲状腺を働かせる指令ホルモン)で、必要に応じてFT4(エフティーフォー:体内で実際に働ける甲状腺ホルモン)を追加します。
妊娠・産後、薬やサプリ(特にビオチン)、海藻のとり過ぎ・造影剤検査などは、数値をゆがめたり、症状を分かりにくくしたりするため注意が必要です。
TSHとFT4って何?
どうやって調べるの?
採血前の注意点
甲状腺の主な症状
働きが弱いとき(甲状腺機能低下)
働きが強すぎるとき(甲状腺機能亢進)
しこり・腫れ(甲状腺結節)
甲状腺の炎症
健診のあと、まずどう考える?
「数値が少しだけ外れている」段階の扱い
健康診断や再検で、少しだけ基準から外れていることがあります。
妊娠・産後での注意(見落としやすい点)
薬・サプリ・検査で“数値がズレる”ことがあります
しこりを指摘されたら(超音波検査の見方の目安)
超音波検査(エコー検査)では、しこりの中身の性質・明るさ・形・ふちの様子・点々の強い光などを組み合わせて危険度を判断します。
細い針で細胞をとる検査(細胞診)は、一般にしこりの大きさと危険度で決めます。
受診の目安
次のいずれかに当てはまる場合は、内分泌内科・甲状腺外来・一般内科などの医療機関へご相談ください。
緊急の目安(救急受診も検討)
まとめ
数値が少しだけ外れている段階でも、再検のタイミング(3〜6か月)と体調の変化をていねいに追うことで、早めに適切な対応ができます。