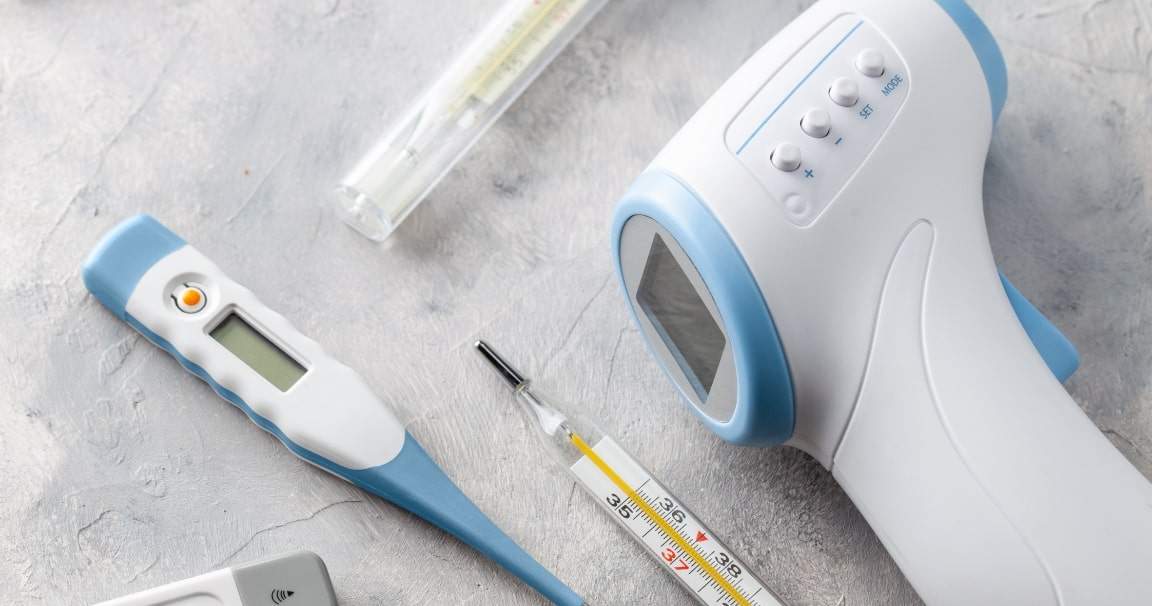- エアコンは「つけっぱなし」が正解
電気代が気になるところですが、健康への投資と考え、朝までつけっぱなしにすることをお勧めします。タイマーで切ってしまうと、室温の上昇で夜中に目が覚める原因になります。設定温度は
26~28℃、そして何より湿度を60%以下に保つことが重要です。寝る30分~1時間前から部屋を冷やし始め、壁や天井の熱を取っておくとさらに効果的です。 - 扇風機は「間接的」に使う
風を直接体に当て続けると、体が冷えすぎてしまい、かえって自律神経を乱す原因になります。壁や天井に向けて、部屋の空気を優しく循環させるように使いましょう 16。 - 寝具は「天然素材」を選ぶ
パジャマやシーツは、汗をしっかり吸って外に逃がしてくれる、綿や麻(リネン)などの天然素材がおすすめです。 - 入浴は就寝の「1~2時間前」に
38~40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。入浴で一時的に上がった深部体温が、お風呂上がりに急降下するタイミングで、強い眠気が訪れます。シャワーで済ませる場合も、手首や足首、首の後ろに少し熱めのシャワーを当てると同様の効果が期待できます。 - 夕食は「就寝3時間前」までに
寝る直前の食事は、消化活動が睡眠を妨げます。夕食は軽めに済ませましょう。また、コーヒーやお茶に含まれるカフェインは覚醒作用が長いため、就寝の5~6時間前からは控えるのが賢明です。 - 寝る前の水分補給を忘れずに
睡眠中は汗で多くの水分が失われます。脱水を防ぐため、就寝前にコップ1杯の常温の水を飲む習慣をつけましょう。 - 就寝1時間前は「デジタル・オフ」
スマートフォンやパソコンの画面から出るブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げます。寝る前の時間は、画面から離れて過ごしましょう。 - 自分だけの「入眠儀式」を
穏やかな音楽を聴く、紙の本を読む、軽いストレッチをする、アロマを香らせるなど、毎日決まった行動をすることで、脳に「眠る時間だ」という合図を送ることができます。 - 「4-7-8呼吸法」で心を落ち着ける
ベッドに入ったら、「鼻から4秒吸って、7秒息を止め、口から8秒かけてゆっくり吐き出す」という呼吸を数回繰り返してみてください。副交感神経が優位になり、驚くほど心身がリラックスします。
「なぜ夏はぐっすり眠れないの?」熱帯夜の睡眠科学
夏の夜、寝苦しさで何度も目が覚めたり、朝起きても疲れがすっきり取れなかったり。「夏だから仕方ない」と諦めていませんか?実はその寝苦しさには、科学的な理由が隠されています。
今回は、多くの方が悩まれる「夏の睡眠」について、そのメカニズムと、今日からすぐに実践できる具体的な対策を、医学的な視点から分かりやすく解説していきます。
なぜ夏は眠りが浅くなるのか?3つの科学的理由
私たちが快適に眠るためには、体の内部でいくつかの重要なスイッチが切り替わる必要があります。しかし、夏特有の環境は、これらのスイッチがうまく働くのを邪魔してしまうのです。
理由1:下がらない「深部体温」
私たちの体は、眠りに入るために、脳や内臓の温度である「深部体温」を下げる必要があります。日中の活動で上がった体温を、主に手足から外へ逃がすことで、体は自然と休息モードへと切り替わります。
しかし、夏の夜は「高温」と「高湿」という二つの壁が立ちはだかります。気温が高いと体から熱が逃げにくく、さらに湿度が高いと、体温を下げるための最も有効な手段である「汗の蒸発」が妨げられてしまいます。汗が蒸発する時に体の熱を奪ってくれるのですが、湿度が高いと汗がただ肌を濡らすだけで、冷却効果が発揮されません。その結果、深部体温が十分に下がらず、「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」といった状態に陥ってしまうのです。
理由2:乱れる「体内時計」
私たちの体には、約24時間周期の「体内時計」が備わっており、夜になると自然な眠りを誘う「メラトニン」というホルモンが分泌されます。
夏はこの仕組みにとって不利な季節です。まず、日照時間が長いため、メラトニンの分泌が始まる「夜」の時間が短くなります。また、夜遅くまでスマートフォンやテレビの明るい光、特にブルーライトを浴びていると、メラトニンの分泌が強力に抑制され、脳が「まだ昼だ」と勘違いしてしまいます。体内時計を整えるためには、朝に太陽の光を浴びて時計をリセットし、夜は穏やかな暗さの中で過ごすことが大切なのです。
理由3:酷使される「自律神経」
体温調節や心臓の動きなど、生命維持に欠かせない機能を無意識にコントロールしているのが「自律神経」です。自律神経には、活動モードの「交感神経」と、リラックスモードの「副交感神経」があります。質の良い睡眠のためには、夜になると副交感神経が優位になる必要があります。
しかし夏は、猛暑の屋外と冷房の効いた室内を頻繁に行き来することで、自律神経に急激な切り替えが強いられ、神経が疲弊してしまいます。この負担が続くと、夜になっても交感神経が優位な状態が続き、体は疲れているのに頭は冴えている、という「疲れているのに眠れない」状態を引き起こしてしまうのです。
睡眠不足が招く「夏バテ」との悪循環
夏の睡眠不足は、日中の眠気だけでなく、「夏バテ」と呼ばれるさまざまな不調の引き金になります。全身の倦怠感、食欲不振、集中力の低下、イライラ感などがその代表的な症状です。
睡眠が足りないと、体の疲労回復や細胞の修復が追いつかず、夏バテの症状が悪化します。さらに深刻なのは、夏バテによる自律神経の乱れや栄養不足が、さらなる睡眠の質の低下を招くという「負の連鎖」です。この悪循環を断ち切ることが、夏を元気に乗り切るための鍵となります。
熱帯夜でも快眠するための「3つの処方箋」
では、どうすれば夏の夜に質の高い睡眠をとることができるのでしょうか。原因である「体温」「光」「自律神経」の3つにアプローチする、具体的な方法をご紹介します。
処方箋1:睡眠環境を「コントロール」する
寝室を、眠りのための「聖域」に整えましょう。
処方箋2:眠りにつなげる「生活習慣」
夜の睡眠の質は、日中の過ごし方で決まります。
処方箋3:心と体を「リラックス」させる
脳を活動モードから休息モードへ、穏やかに切り替えましょう。
最後に
夏の睡眠不足は、単なる寝苦しさの問題ではなく、心と体の健康に深く関わっています。今回ご紹介した対策をいくつか試していただくだけでも、睡眠の質はきっと改善されるはずです。
もし、セルフケアを試しても不眠が続く、日中の眠気がつらい、あるいは気分の落ち込みが強いなど、お悩みが改善しない場合は、決して一人で抱え込まないでください。当クリニックでは、睡眠に関する専門的な診療を行う睡眠外来や、ストレスに伴う不眠に対応する心療内科もございます。どうぞお気軽に、私たちにご相談ください。
この夏、皆さまが健やかな毎日を送れるよう、心から願っております。